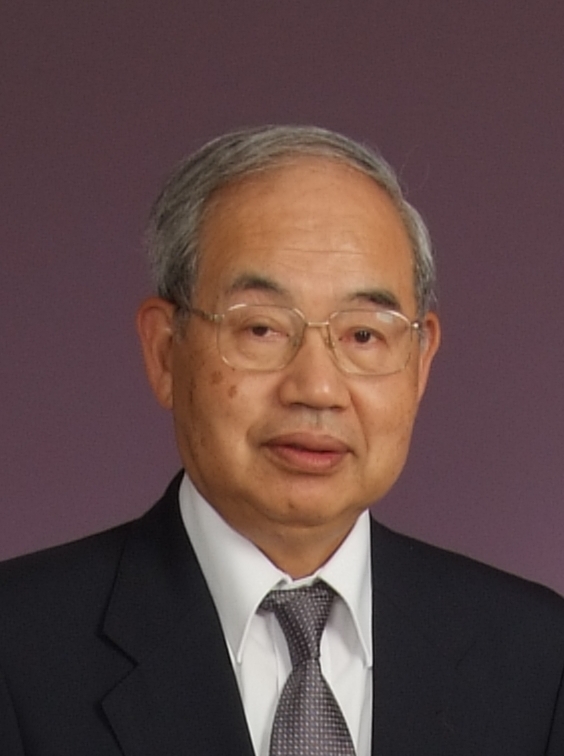明治日本の産業革命遺産は偉大な教材、覗けば見えてくる様々な世界
元新日本製鐵株式会社社員、世界遺産登録推進室産業プロジェクトチームメンバー
詳しくお話しいただけますでしょうか。
「鉄は国家なり」という言葉の由来はプロイセンのビスマルク首相が1862年議会下院予算委員会においてドイツ統一に向け、「国家は鉄と血によって贖われる。議会で議論を繰り返しても何も生まれない。血と鉄すなわち武力によって統一は実現する」と説いた鉄血演説に由来するといわれています。この言葉から鉄=武力=軍事=国家とイメージされてしまいますが、国家の近代化、あるいは近代国家の成立と鉄の製造技術およびその製品の進歩とは密接に絡み合っています。
18世紀末、英国において錬鉄(パドル鉄)が登場します。錬鉄は機械製作や建築・土木の建設に画期をもたらし、産業革命の原動力となりました。こうして英国は18世紀末から19世紀の過半、大帝国として繁栄を極めました。19世紀後半になると転炉法や平炉法が開発され、溶鋼の時代を迎えます。溶鋼は均質な鋼の大量生産を実現しました。転炉法は英国人ベッセマーによって1856年に発明されました。当時の転炉は鉄道レールの製造に適していて、また米国にはベッセマー転炉による溶鋼製造に適した鉄鉱石が豊富にありました。西部開拓のこの時代、ベッセマー転炉は大陸横断鉄道建設に必要な大量のレールを供給、ついにはフロンティアをなくし、広大な米国に国家としての一体性が生まれることに大きく寄与しました。
1877年、英国人G. トーマスが塩基性の転炉・平炉の製造に成功します。これにより、製鋼工程での燐分除去が可能となり、ベルギー、ルクセンブルク、独仏国境地帯(ルール・ザール)の豊富な鉄鉱石(ミネット鉱)を使って溶鋼を大量生産することができるようになりました。溶鋼生産量においてドイツはたちまち英国をキャッチアップして優位にたちます。溶鋼で造られた鋼材は錬鉄製に比べ機械的性質・耐久性に富み、鉄道敷設距離1キロの鉄使用料を半減させました。鉄道網に代表される物流の充実は何よりも国家に一体性を与えるとともに市場規模の拡大をもたらし、国家経済のスパイラル的拡大をもたらします。この効果を享受したのが、欧州では新興ドイツであり、ベルギーでした。この塩基性の転炉・平炉の出現は技術的には改良レベルの出来事だったかもしれませんが、欧州世界の勢力図を変えたという意味ではシュムペーターの定義するイノベーションの教科書的事例と言っても過言ではないでしょう。塩基性の転炉や平炉の開発で燐分除去が可能になった結果、錬鉄は鎖やリベット等の材料に限定され表舞台から退場を余儀なくされました。
製鉄・製鋼には石炭を必要とし、鉄道や船舶輸送にはその製作とインフラ整備に鋼材を必要とし、輸送の際には大量の石炭を消費し、石炭採掘には鋼材や船舶鉄道の輸送網の整備が必要と、こうした産業の連関は補完関係にあり、その補完関係を造ることが国家の近代化が実現する条件だったいえます。
国家の近代化と製鉄・製鋼の進歩、鉄道・船舶等の物流、石炭採掘は切り離して考えられないのですね。
製鉄・製鋼の進んだ欧米から遠く離れた日本では「鉄は国家なり」という言葉はまた別の意味を含んでいると私は考えています。日本では官営釜石製鉄所において錬鉄とその製品の製造をめざし、官営八幡製鐵所において溶鋼とその製品である鋼材の製造をめざしました。欧米諸国では製鉄・製鋼事業の蓄積がありますので、鋼材を製造するに必要な製鉄、製鋼、圧延の三つのステップを分解して工程ごとの事業化が可能であったのに対し、後進国であった日本では高炉による銑鉄製造、転炉・平炉による溶鋼製造、用途別鋼材を製造する各種圧延工場を一挙にそろえないと最終目的である鋼材の製造が果たせませんでした。このためには巨額の資金と人材の育成、さらにはリスクテイクが必要となり、民間レベルでの事業化はとても無理でした。
また当初鉄鉱石は国内で全てを調達する方針でしたが、結果的には中国湖北省の大冶(だいや)鉄鉱石を主要鉱石とすることになって行きました。湖北省政府との交渉、鉱石採掘のための資金供与、中国鉄鉱石の欧米資本の利用阻止など、外務省・大蔵省の全面的なバックアップを必要とし、製鉄所を建設するだけでなく、その操業をすることにもまた政府の機能を活用しなければなりませんでした。少し具体的なお話を申し上げますと、官営八幡製鐵所は当初、原料を新潟県の赤谷と岩手県の釜石の鉄鉱石で賄う予定でしたが、中国側から武漢の近くの長江下流の大冶鉄山の鉱石を買わないか、替わりに日本の石炭が欲しいという提案がありました。その話に小村寿太郎の懐刀と言われ上海領事であった小田切万寿之助が敏感に反応します。ちょうどその時にドイツの専門誌に同国の鉱山技師が、「中国の大冶に大量の鉄鉱石がある。この鉄鉱石を使ってドイツ資本の製鉄所を作るべき。東洋のマーケットを押さえるために、今こそ中国に金を投じて上海あたりに製鉄所を作るのがいいだろう」と寄稿していました。これを知った日本は、そんなことをされたら今造ろうとしている官営製鉄所計画が吹っ飛んでしまうので大治の鉄鉱石を確保しようという話になります。小田切領事の機敏な働きにより明治32年(1899年)に大冶鉄鉱石購入契約が結ばれました。この契約には、清国側は清国内における外国資本の製鉄所には大冶鉱石を販売しないという極めて重要な項目が含まれています。
製鉄業というのは国家をあげて行わなければ動かなかったのですね。
ええ。官営八幡製鐵所は農商務省に属しているわけですが、他の国家機関との関わり合いについて、例えば海軍工廠との役割分担などについての歴史研究はかなりされているのですが、他の省庁と官営八幡製鐵所との関わり合いについては、私の知る限りあまり突っ込んだ調査は行われていないのではと思います。海軍、陸軍、鉄道、内務、大蔵、文部省は大きな需要家ですし、資金面では大蔵省、海外の原料調達や鉄鋼事情の把握等については外務省等の全面的なバックアップを受けていましたが、その詳細について詳しい研究はないのではと思います。
現代人が歴史から学ぶこともありそうですが。
たとえばCO2の問題。周知のようにCO2の問題で鉄鋼業危うしと言われているわけです。先日も新聞に日本製鐵が技術改革を導入し、2030年には二酸化炭素排出量を30パーセント削減、2050年のカーボンニュートラルを目指すという記事が出ていました。高炉法以前の製鉄法は鉄鉱石を固体のまま還元する方法で、二酸化炭素を排出しますが、原理的に排出規模はかなり小さかったと思います。この古代製鉄法の原理は直接還元法として現代でも小規模の製鉄には使われていて、その高度化が可能なものか今注目されています。実は製鉄・製鋼法の歴史をたどると数々の試行錯誤の歴史であることがわかります。
ある意味死屍累々といった感もあるのですが、その中からよみがえってくるものもあるのではと少し期待しています。またオオカミの遠吠えと言われそうですが、「宇宙の歴史と鉄元素の誕生」、「地球の生命体と鉄」、「磁性体としての鉄と現代文明」といった観点も踏まえたCO2削減議論もあるべきだと考えています。
Vol.60
「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録10周年お祝いメッセ―ジ
一般財団法人産業遺産国民会議代表理事
(九州旅客鉄道株式会社 名誉顧問)
Vol.59
~産業遺産情報センターの主任研究員として、文化遺産の魅力を発信~
産業遺産情報センター主任研究員
日本鉱業株式会社 名誉顧問
釜石応援ふるさと大使
Vol.58
世界遺産を守っていくために必要なのは本質的なことを見落とさない視点
一般財団法人長崎ロープウェイ・水族館理事長
前、長崎市世界遺産推進室室長
Vol.57
日本の未来のために今を生きる~明治日本の産業革命遺産の使命は「先人のスピリットを活かしていけば日本は救われる」という気づきと勇気を与えること
Vol.56
明治日本の産業遺産は日本の誇り~先人たちの歩みを知ることは日本の教育を見つめ直すことに通じる
フジサンケイグループ 代表
株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役
株式会社フジテレビジョン 取締役相談役
Vol.55
世界遺産登録までの道のりは、山あり谷ありだった~人の縁という運に恵まれ、救われ、道を拓いて~
日本港湾空港建設協会連合会 顧問(元、一般財団法人 港湾空港総合技術センター理事長)
Vol.54
『侍が、カンパニーへ』という歴史的流れは日本の誇り~明治日本の産業遺産の中心的存在である長崎がリードして次世代へつなぐ
Vol.53
日本で初めて反射炉を作った佐賀藩、洋式海軍の拠点だった「三重津海軍所」~世界遺産登録に注いだ情熱を次世代に繋ぎたい。
前、佐野常民記念館(現、佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館)館長
Vol.52
八幡製鉄所は、今も世界最先端のものづくりを作り続ける現役製鉄所
一般財団法人産業遺産国民会議 理事
特定非営利活動法人 里山を考える会 理事
Vol.51
吉田松陰や幕末の志士たちの熱き想い、急速な産業化を通して日本を支えた優れた功績 ~ 松陰神社には明治維新に至る歴史をきちんと伝えていく使命がある
Vol.50
稼働資産「三池港」を世界遺産にする秘策とは。
Vol. 49
明治日本の産業遺産に関する保全マニュアルの重要性とは?
Vol.48
金属学の視点から紐解いて明らかになった産業史の真実~日本人の聡明さ、勤勉さ、不屈の精神を次世代へ伝えることが明治日本の産業革命遺産の使命~
Vol.47
明治日本の産業革命遺産は偉大な教材、覗けば見えてくる様々な世界
元新日本製鐵株式会社社員、世界遺産登録推進室産業プロジェクトチームメンバー
Vol.46
鹿児島から始まった鉄の歴史が日本の近代化を飛躍的に前進させた~薩摩人のバイタリティを、未来に生きる若い世代に引き継いでいきたい~
Vol.45
吉田松陰が工業教育論を説き、命がけで英国へ渡った長州ファイブを輩出~誇らしき萩スピリットを後進へとつなげるために~
Vol.44
三角西港を作った先人の知恵、技術、行動力を子供たちの代へと継承していきたい~コロナ後も続く未来を見据えて今できることに全力で取り組む~
Vol.43
官営八幡製鐵所は「1枚の古写真」から世界遺産になった!~元日鉄マンが明かす、"登録前夜"のとっておきのエピソード~
Vol.42
外に向かって発信する「新しい地元学」を確立したい ~「釜石の誇り」から「日本・世界の中の釜石の誇り」へ!~
Vol.41
観光ガイド歴18年、あふれ出る"三角西港愛"~世界遺産登録はゴールではなく、新たな出発点~
Vol.40
韮山反射炉とともに「刻」をきざむ~物産館&レストラン事業で"反射炉観光"の魅力度アップ~
株式会社蔵屋鳴沢 代表取締役社長
一般社団法人伊豆の国市観光協会会長
Vol.39
運命に導かれて軍艦島デジタルミュージアムを設立~明治日本の産業革命遺産の価値を広く深く伝えるために、自分にできることを始めて、続けて、やり切りたい~
軍艦島コンシェルジュ取締役統括マネージャー
軍艦島デジタルミュージアムプロデユーサー
Vol.38
産業遺産の主役は「人」~世界遺産登録を経て再認識した故郷の素晴らしさ~
Vol.37
すべては長崎の経済発展のために~海運業の枠を超え、長崎の文化や産業遺産の歴史を伝承~
Vol.36
釜石の奇跡と、震災を乗り越えて~世界遺産登録という大きなチャンス~
Vol.35
韮山反射炉とともに後世に伝えたい「850年の歴史資料」 ~待望の新・収蔵庫が完成、保存・修復・活用に弾み
Vol.34
不屈の開拓精神と先人のパワーで時代を切り拓いた歴史~後世へ受け継がれる希望と大きな力~
Vol.33
軍艦島は「地球と人類の未来への警告のメッセージ」~元島民ガイドが訴える想いと願い~
Vol.32
「シンクロニシティー」が生んだ世界遺産登録という奇跡~想いの強さが志ある人々の共感を呼び起こした!~
エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社 代表取締役
Vol.31
日本の人達にパワーを~明治日本の産業革命遺産の使命~
渡辺プロダクショングループ代表・株式会社渡辺プロダクション名誉会長
Vol.30
産業遺産の歩みを"100年後を生きる人々"への希望に
Vol.29
"21世紀の薩摩ステューデント"よ、未来を創れ!~旧集成館は鹿児島観光の情報発信拠点~
Vol.28
各地域に着実に広がる「つながりあるストーリー」という意識~保全管理・インタープリテーションのあり方には課題も~
サラ・ジェーン・ブラジル(Sarah Jane Brazil)氏
Vol.27
《為せば成る為さねば成らぬ何事も》~人とつながるための勇気や行動力を~
特定非営利活動法人 九州・アジア経営塾 理事長兼塾長
株式会社SUMIDA 代表取締役
Vol.26
「日本人として、世界に対して誇りを持って発信できる世界遺産」〜内閣官房・有識者会議の流れを決したジャーナリストの視点〜
Vol.25
クラシックカーが「明治日本の産業革命遺産」を走る!~2019年、九州で「ラリーニッポン」を開催~
Vol.24
着々と進む"世界遺産周遊ルート"の整備・振興 ~推進協議会、多彩なプロモーションで世界に向けて魅力発信!~
明治日本の産業革命遺産世界遺産ルート推進協議会会長
一般財団法人産業遺産国民会議理事
(九州旅客鉄道株式会社 相談役)
Vol.23
「遺産観光」の振興に向けたルート整備にいっそうの力を~忘れ難い故郷・呉への空襲と広島原爆の記憶~
一般財団法人産業遺産国民会議 代表理事
(公益財団法人資本市場振興財団 顧問)
Vol.22
世界とつながる町~"長崎のたから"を"世界のたから"へ~
Vol.21
「ICOMOS-TICCIH共同原則」の真価問われる"世界の実験場"~日本政府が推進する新たな保全へのチャレンジ~
Vol.20
忘れ難いS・スミス氏との激論の日々 ~異文化の中で出会った"なじみ深い19世紀の産業遺産"~
Vol.19
歴史や文化を継承することは、次世代の技術革新を生み出す~"使いながら残す"に道を開いた「明治日本の産業革命遺産」~
Vol.18
シリアル登録方式の保全管理に新たな道を拓いた「明治日本の産業革命遺産」-- 今後の大きな課題は「記憶と理解を引き継ぐ人材研修」
ヘリテージ保全並びに世界遺産の専門家としてグローバルに活躍する国際コンサルタント
ダンカン・マーシャル(Duncan Marshall)氏
Vol.17
ジャイアント・カンチレバークレーンと小菅修船場跡の3Dデジタル・ドキュメンテーション
The Glasgow School of Art’s School of Simulation and Visualization、データ・アクイジション責任者
Vol.15
「スコティッシュ・テン プロジェクト」によるデジタル文書化
ヒストリック・スコットランド
スコティッシュ・テン プロジェクト・マネージャー
Vol.14
富士山と韮山反射炉、2つの世界遺産を一望できる茶畑の丘 --次の夢は「子どものためのミニ反射炉」で体験学習
Vol.13
登録までの道のりと資産の今後を見つめて
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート副学長・評議会議長
イングランド・ウェールズにおけるカナル&リバートラスト遺産顧問
Vol.12
正確な情報発信の中で、歴史を見つめるきっかけに
Vol.11
「ものづくりの街・北九州」への愛着と誇り--"シビック・プライド"を呼び起こしてくれた世界文化遺産登録
Vol.10
世界遺産登録決定祝賀会レポート(@ドイツ・ボン)
2015年6月28日から7月8日まで、ドイツ・ボンにて第 39 回世界遺産委員会が開催され、「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録が決定しました。
今回は、世界遺産登録決定祝賀会の様子をお伝えいたします。
Vol.9
使いながら保存する-「稼働遺産」の保存・活用に新たな道を拓く
阪神高速道路株式会社 取締役兼常務執行役員
(一般財団法人産業遺産国民会議 理事)
Vol.8
港湾法の体系で、世界遺産の保全を担保する
Vol.7
近代化を切り拓いた長州ファイブと試行錯誤の痕跡を残す萩の資産
Vol.6
日本の「ものづくり」「産業」の原点を伝える「明治日本の産業革命遺産」
Vol.5
日本の近代工業化を石炭産業によって支えた三池エリア
Vol.4
国家、社会のため、広い視野と使命感を持って試行錯誤しつつ挑戦し続けた「明治の産業革命」の意義
文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習総括官
前 内閣官房 内閣参事官
Vol.3
「鉄は釜石から八幡へ」 近代製鉄発祥の地から誇り高き文化を伝える
Vol.2
強く豊かな国家を目指して 薩摩藩主島津斉彬が築いた『集成館』
一般財団法人産業遺産国民会議 理事
島津興業 相談役
Vol.1
産業国家日本の原点 『明治日本の産業革命遺産』を次世代へ
「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会 会長/鹿児島県知事